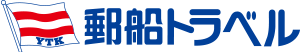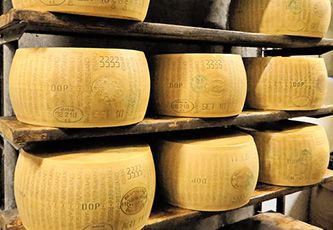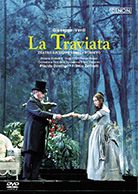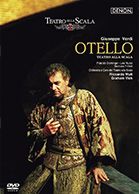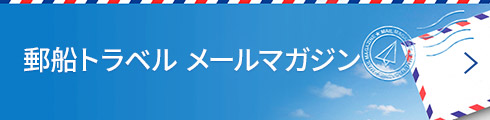Broadcasting Corporation 2012
『カルテット!人生のオペラハウス』
発売中
発売元:ギャガ
販売元:ポニーキャニオン
価格:Blu-ray ¥4,700+税
監督:
ダスティン・ホフマン
出演:
マギー・スミス/トム・コートネイ/ビリー・コノリー/ポーリーン・コリンズ/マイケル・ガンボン 他

名優ダスティン・ホフマンの初監督作。舞台はイギリスの田舎町。のどかな大自然の中、引退した音楽家たちが暮らす「ビーチャム・ハウス」で穏やかな余生を送るレジー、シシー、ウィルフ。ところが、かつて野心とエゴで仲間を傷つけ去って行ったカルテット仲間のジーンが、新入居者としてやってくる。近く、ビーチャム・ハウスの経営難を救うために開かれるガラコンサートを成功させるべく、誰もが伝説のカルテット復活に期待を寄せるが、かつてオペラ界で活躍した彼らも、今や認知症や持病を抱えていて、稽古すら思うようにいかない。さらに、過去の栄光に縛られたジーンは歌を封印してしまう。果たして伝説のカルテットは再結成なるのか―。
ヴェルディに学ぶオペラの世界と
憩いの場を巡る旅
音楽に悩み、音楽に救われる人生
ホームの存続を懸けて開催するガラコンサートに向け、懸命に準備を進める入居者たち。目玉のプログラムは、かつての四大スターによるカルテット『美しき愛らしい娘よ』です。しかしこのカルテット、一筋縄ではいきません。認知症で場を騒がせるお茶目なシシー、ホームのスタッフを片っ端から口説くウィルフ、若かりし頃結婚し、たった9時間で離婚してしまったレジーとジーンの関係性など、個性溢れるメンバーによる人間ドラマがコメディータッチで繰り広げられる一方で、特に大スターとしてその名をはせていたジーンが、今は老いた体とかつての栄光のはざまで葛藤する姿が、生々しく描かれています。
常に厳しい批評の目にさらされ、歌うことをやめてしまったジーンに対し、レジーが提示したのは「芸術作品とは無限の孤独であり、さまつな批評など手が届かないものである」という格言。彼らの現役時代が劇中で語られることはありませんが、控えめに「ありがとう」と言ったジーンとレジーの間には、お互いに似た景色を見てきたからこそ共有できる苦楽があり、戦友にも近いような関係性であることがうかがえます。
さて、劇中で企画されていたコンサートは、19世紀ロマン派の人気作曲家としてオペラ史においても重要な役割を果たしたジュゼッペ・ヴェルディ生誕200周年を祝うものでした。
実は入居者の役で出演しているメンバーの多くが実際の著名アーティストたちであることは、本作の大きな見どころの一つ。劇中では≪椿姫≫から『乾杯の歌』、≪トスカ≫から『歌に生き、愛に生き』、≪ミカド≫から『学校帰りの三人娘』などが彼らによって見事に演奏されています。監督を務めた名優ダスティン・ホフマン氏がメイキング映像内で「人生がその人の顔を作る」と語っている通り、彼らの表情はとても豊かで生き生きとしており、作品のテーマに奥行きをもたらしています。
メインストーリーに直接関わるところではありませんが、序盤でレジーが学生を相手に講義をするシーンも印象的です。彼らが好んで聴くのはレディ・ガガやラップ、ヒップホップなど。これらは一見、オペラとは縁のないもののように思えますが、レジーは「かつてオペラの観劇スタイルは、普段着で食べ物やお酒を持って入り、物を投げたりする人もいたほど大衆的なものだった」と説明します。さらに、「オペラとは誰もが内面に持つ感情の激しいとばしりなのだ」と話すと、それを聞いた若者が、「オペラとラップは同じ、痛みを語る人間の内側からのサインだ」とラップで返答。これにはレジーも他の学生たちも、視聴者である私たちもハッとさせられます。オペラは今でこそ敷居の高いイメージですが、どんな年代やジャンルでも、音楽が表現しているのはシンプルに「人間の内面」なのだということは、この映画が語りたかったメッセージの一つなのではないでしょうか。
現地を訪ねたら見逃せない、
みどころと名物
-

ミラノ大聖堂 -

ミラノのトラム -

ヴェルディ生家